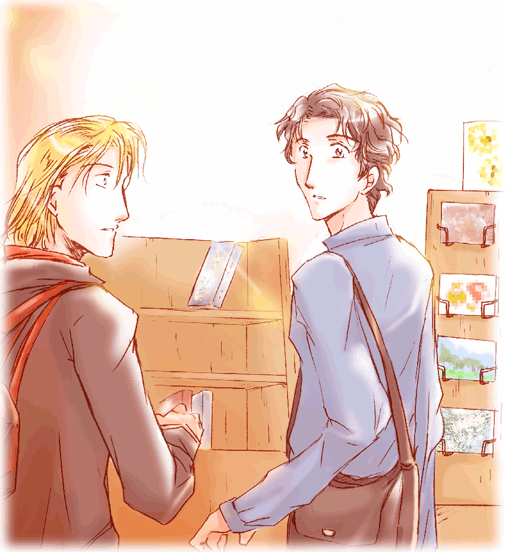
急ぐものでもないからと、アブナーはその日の移動をあえて列車にした。
飛行機ならほんの1、2時間の距離なのに、わざわざ移動を1日仕事にするなんてクレイジー!とみんなには言われたけれど、
たまにはのんびり車窓を眺めるような時間があってもいい、と思い退屈するために切符を取った。
列車に向かう人の群れを見るに、それなりに乗客は多そうだったが、始発から終点まで8時間もかけて行こうなんて物好きは、
きっと自分くらいのものだろうと思うと自然と笑みがもれた。
発車までの時間をつぶすべく売店をひやかした。お茶や食べ物は、車内でも買えるだろうし途中の駅で買ってもいい、
でももしもということがあるし口寂しくもなるだろうと、ジンジャービスケットのは小さな箱をひとつとりんごをひとつ、それからオレンジジュースを買った。
これだけあれば非常食になるだろう。
それがすむと今度は、くるくる回るラックに満載の絵ハガキに目がいった。きれいな都市の写真やかわいらしい動物の写真、
その中にある赤ん坊の写真に手が伸びそうになった。もうすぐ生まれる子供とその母親のことを思った。
すぐにも飛んでいきたい思いにかられることもあったが、故国はあまりに遠すぎた。今の自分には、とても。
なにしろこうして、列車で行くことがかなわないのだから。
アブナーはため息をつきながら子供の写真から目をそらした。絵ハガキのラックのとなりには、ペーパーバックがあった。そういえば、
列車で読むようなものが何もなかった。ぼんやり外を眺めていればいいとは思うが、雑誌か軽い読み物のひとつもあってもいいかもしれない、
とアブナーはまずはペーパーバックを物色しはじめた。
(あ、そういえばあの本まだ読んでなかったな)
好きな作家の新刊で、そのうちそのうちと思っている間にすっかり時間がたってしまっていた。よく見かけるので大丈夫だろうと安心していたら、
いつの間にか1冊だけになってしまっている。
(この機を逃すと見つからないかも……買っておこ)
たとえ車内で読まなくても、いつかは読むだろう、そう思って手を伸ばした。すると。
「あ」
「失礼」
伸ばした手がかちあった。
どうやら同じ本を取ろうとしたかららしかった。
もう出て大分たつその本は下のほうにあって、隣近所は空になっていたので、他の本とも思えない。アブナーも相手も少し手を引っ込めたものの、
さてどうしようかと思案しているような空気がそこにはあった。
「……失礼ですが、この本ですか?」
「……この本なんです」
相手もアブナーと同じくらいの男で、明るい金色のに青い瞳、はっきりとした顔立ちはとても在来種には見えなかった。その男が今、
すまなそうな目をしてアブナーを見ていた。その目にアブナーは、なんだか太陽が翳ったみたいだ、と思った。
「……好きな作家なんです」
「……列車で読もうかと思って」
悩んだ末に、出来たら譲りたくない思いを2人は同時に口にした。
「好きな、作家?」
「ええ……」
男はそれを聞くと顎に手をやり考え込んだ。そして。
「それならどうぞ。面白いという話を聞いて、ちょっと興味を持っただけだから」
「え、でも……」
譲られると今度は猛烈に申し訳ない気がしてきて、アブナーは戸惑った。
「何もペーパーバックじゃなくても構わないし、健康雑誌にでもしときます。最近少し腹が出てきているし」
どこから来たのか少しもこもこした格好をしていたが、前の開いているコートから見る様子は本人が気にしていると言うほど身体の線が丸いとも思えなかった。
「じゃ」
そう言って男は、アブナーの手にそのペーパーバックを乗せると、軽く手を上げて雑誌のコーナーへと向かっていった。
「あ、ありがとうございます!」
これだけは言っておかなくては、とアブナーは大きな声でそう言った。他の客がなんだなんだ?という目でアブナーを見たが構わなかった。
男は、アブナーに背を向けていたけれど肩に背負った荷物のないほうの手を上げて、アブナーの感謝に答えた。
駅舎の天窓から入る陽を受けて、少し長めの男の髪はきらきらと輝いていた。
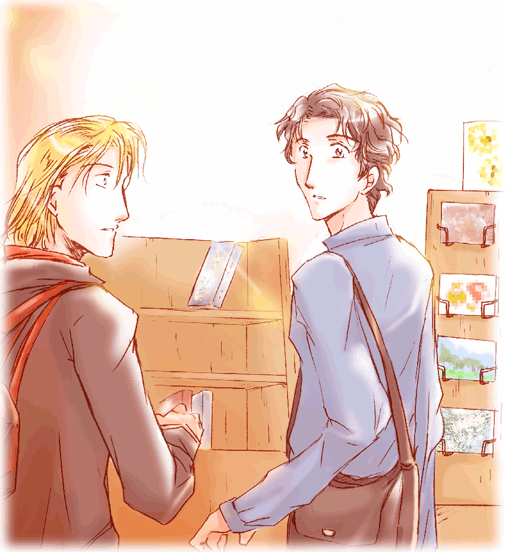
「あ……」
「さっきの……」
追いかけてきちんと礼を言う出べきだろうかと悩んでいるうちに、男は団体客にさえぎられて見えなくなってしまった。
雑誌のコーナーにはもう姿が見えず、ほかの売店に行ったのかもしれないと思いつつ清算を済ませ、あちこちのぞいてみたのだが、
目立つはずの金色の髪はどこにも見当たらなかった。発車ギリギリまできょろきょろしていたのだが、さすがにそろそろ乗っておいたほうが、
という時計のアドバイスを受けて入れて、列車に乗り込んだアブナーだった。なんだかむしりとったみたいで悪いことしちゃったなあ、
別にどうしてもここでないとないというんでもなかったろうに、なんて大人げないことをしてしまったんだろう、
アメリカ人ぽかったけど、きっとこっちの印象を悪くしたんじゃなかろうか、とくよくよ考えながら席を探していると。
「さっきはどうも、ありがとうございました」
ともかく、これだけは言わないと、と思っていたものだから、驚きよりも何よりも、それだけはするっと口をついて出た。
「とんでもない」
男は、照れたようにそう言った。席は、一応決まっていたが2、3割程度しか埋まっていないこの状態では、移動しようとなにしようと自由だった。
ボックス席の真ん中にあるテーブルには、男が買ったのだろう雑誌があって、荷物も何もないところを見ると連れはいないし向かいの席は空いているようだった。
でも、他の席も空いていた。もちろん、アブナーの到着を待っている向こうの席も。男の前の席に座りたい、という強烈な欲求があった。しかし、
なんと言って?おかしく思われやしないだろうか?さっきちょっと売店で行き会っただけなのに、そんなことを言ったら迷惑ではないだろうかと思うと、
アブナーは立ちすくんだまま動くことが出来なかった。
男は立ったままでいるアブナーに、どうかした?というように小首を傾げて広げていた新聞に目を戻す様子はなかった。なおさら居たたまれなく思っていると、
列車ががくんとゆれた。発車したようだった。
「座ったら?」
男がそう言ってくれたのを、アブナーは天の助けとばかりに受け入れた。
「あ、ああ……」
座ったら警報でも鳴るんじゃないかと思いながら、こわごわとアブナーは向かいのイスに座った。座り心地も何も、あったものではなかった。
アブナーが座るとたまたまその席なのだと思ったようで、男はまた新聞に目を戻した。アブナーはじっと見ているのもまずいと思ってとりあえず
ビスケットを取り出して、さして食べたくもないのに一口齧った。
「……っっ」
そんな心ここに非ずの食べ方をしたのがいけなかったのか、ビスケットなのがいけなかったのか、ビスケットの粉末が気管に入り込み、
アブナーは思い切り咳き込んだ。
「どうしたっ」
押さえようと思っても押さえられなかった。
身体が求めるだけ、盛大にごほごほとやっていると、男が飛んできて背中をさすってくれた。その手のぬくもりを得がたく感じていると、
男はアブナーがテーブルに置いたジュースの蓋を断って開けると、アブナーの口元にあてがった。
有難くその親切を受けると、やっと咳の発作はおさまっていった。
「あ……り、がとう……ございます……」
まだ少し喉に異物感はあったが、ジュースのおかげでやっと声が出せるまでになった。
男は、よその席からのなんだなんだ?という視線に大丈夫だからとサインを送っているようだった。
「いきなりそんなもの食べるから」
腹が減ってるのか?と席に戻りながら男は笑って言った。笑ってくれたので、アブナーも少し安心することが出来た。
「そういうわけじゃないんですけど……すみませんでした」
本当に腹が減っているかどうかはともかく、迷惑をかけたことは確かなので素直に詫びた。
「どういたしまして」
男はまた、にっこり笑ってそう言ってくれた。
「じきに車内販売が来るだろうから、お茶でも飲みながらにしたほうが……余計なお節介だなこりゃ」
そこまで言って、男は頭をかきかき失礼、と言った。
「そんなことは……」
アブナーがそう抗弁しようとしたところへ、2人のいる車両に車内販売が入ってきた。アブナーはそれを呼び止め、飲み物は何があるかを訊ねた。
「コーヒーと紅茶とミネラルウォーター、それからオレンジジュースです」
車内販売の答えはそうだった。
「よかったら一緒にいかがですか?」
アブナーは勇気をふりしぼって言った。
「え?」
「お礼にご馳走させてください。本と、さきほどの」
心臓が激しいダンスを踊っているようだった。もしかしたら顔も赤くなっているかもしれなかった。
さっき咳き込んだときにも頬が赤らむのを感じたが、今のこれはそれ以上だった。
「紅茶でいいですか?」
アブナーの勢いに気圧されるように男はうなずいた。アブナーは長らく待たせたことを詫びつつ車内販売から紅茶をふたつ買った。
「……どうぞ」
湯気の立つ片方を男のほうに押しやりつつ、アブナーはどうしてこんなに緊張するんだろうと不思議に思った。
「ありがとう。なんだか、かえって悪いな」
アブナーも男も、砂糖をほんの少し紅茶に入れた。甘い湯気はかたくなった気持ちをときほぐしてくれるようだった。
「……すみません、はじめての方にこんな……」
紅茶の湯気に誘われて、エリックもようやくそう言うことが出来た。
「なんだか緊張してしまって……」
「あんたも?」
「え?」
湯気の向こうには、どこか決まり悪げな笑みがあった。
「どうやって話しかけたもんかと思ったんだ」
「え……?」
「売店で別れて、まさかまた会えるとは思わなかったから、発車すれば何か機会もあるかな、と……おかしいよな、まったく」
男は苦笑いしながらそう言った。
「そんな、ことは……わたしだって……」
「もしかしてそれで?」
それが、さきほど咳き込んだことを言っているのだと分かって、アブナーは今度こそ真っ赤になった。
「……そう、だと……思いま…す……」
手持ち無沙汰でビスケットに救いを求めてその挙句にあんなことになったことを、アブナーは誤魔化すことが出来なかった。
「や、光栄だな」
男は太陽のようだと思ったあのひとなつこい笑顔を浮かべて手を差し出した。あまりにもてらいのないその様子に、アブナーは気を飲まれたようになってしまった。
しかし、ためらっているのを誤解されたくなくて、アブナーも急いで手を握り返した。
「ブラッドっていうんだ、よろしく」
「あ……エリック、です、よろしく……」
消え入りそうな声になって、アブナーはそう言ったのだった。
退屈するのもまたいいさ、と思って乗った列車の旅だったのにそんなことは全然なかった。
それどころか窓からの眺めよりも早く、時間は過ぎていった。アブナー同様、男――――ブラッドも終点までということだったので、時間はたっぷりあるはずなのに。
アメリカ人であること、骨董屋の手伝いをしているのでこちらには買い付けに来たのだということ、約束から約束まで間が開いてしまったので
時間つぶしのつもりでこの列車に乗ったのだということ、ここの車内販売のマドレーヌは美味いと聞いているので是非食べたいと思っていることなどを、
ブラッドは少しずつ話していった。アブナーも仕事ででかけるということ、そこには少しの間滞在すること、たまにはのんびりしてみようと思って列車に乗ってみたことなどを話した。
あたりさわりのないところを、嘘を交えて。本当の名前も言う訳には行かなかった。ただ、こちらで使っている偽名とは違うものを使ってしまったのが
理解できなかった。どんどんややこしくなるばかりなのに。
そして、そうしなければならないことを、心から残念に思っていた。
停車駅で買ったスープとサンドイッチの食事をするときも、こちらに来てからのおもしろい話をするときも、来るたびにお茶を買っているので車内販売に覚えられてしまったときも、
いつも笑っていた。ここのお茶には笑い茸の成分でも入っているのではないかと囁きあってまた笑った。
まもなく終点であることを知って、心底驚いたのはどちらも一緒だった。
「……この時計止まってたのかな?」
「……この列車、実は超特急だったとか?」
2人して首をひねってみたところで、次の駅が終点なのは間違いようのない事実だった。
窓から見える景色はいつの間にか牧歌的な郊外の風景から馴染み深い街中のものへと変わっていた。
「……どうやら本当のことらしいな」
「……そうらしい」
どこか呆然としながら呟いて、それからお互いの驚いた表情が面白い、とまた笑った。
「おかげで楽しかったよ、ありがとう」
そう言ってブラッドはまた手を差し出した。
「こちらこそ、迷惑じゃなければいいんだけど」
その手を握り返しながらアブナーは言った。
「迷惑だったら、席を代わってるさ」
終点の大きな駅に向かう客は多く、今でこそ席はほとんど埋まっているが、車掌が切符を検めに来たときはまだガラガラだった。そのときに本当は
アブナーの席は全然別であることはバレていた。決まりの悪い思いをしたアブナーを、ブラッドはその時も軽快に笑い飛ばしてくれたものだった。
買いなおした座席は今度こそブラッドの向かいで、でなければ今頃席をかわらなくてはならないところだった。
「せっかく本を買ったのに、無駄にさせちまったな」
「そういえば、そう、だっ、け」
ペーパーバックを買ったことを、すっかり忘れていた。好きな作家なのに、一度も、思い出しもしなかった。
アブナーは愛用のリュックに手を触れた。記念すべき初任給で買った、思い出深い革のリュックを。
「思い出しもしなかった……」
「悪いことしちゃったな」
「いや、こっちこそ。よかったら、これ」
すまなそうにしてみせるブラッドに、アブナーはかける言葉が見つからず、リュックの中からペーパーバックを取り出した。
「いや、それこそとんでもない!損した、って怒ってやしないか?」
おそるおそるブラッドがそう聞いた。冗談ではなく、本当の本気で言っているのか見極めようと、まじまじと見つめるアブナーの視線に、
ブラッドはますます身を縮めた。そして上目づかいにアブナーを見ていた。ブラッドが100%本気であるのを見てとると、アブナーは笑った。
「そんなこと、あるわけないだろう。礼を言いこそすれ」
ありがとう、楽しい時間だったと言えば、ようやくブラッドも身体をほぐした。
「いやよかった。おかしな奴に話しかけられて、せっかく買った本がちっとも読めなかったとか思われてたらどうしようかと思った」
「そんな心配してたのか?本当に?」
「見えなかった?」
「全然」
「そりゃ目がおかしいよ!こんなにピュアでセンシティウなハートが、バクバクいってるってのに気づかないなんて!」
ブラッドは胸に手を当てて言い立てた。まるで己の誠を宣言する、中世の騎士のように。
行き会って気があって、少しばかり世間話をするのはよくあることだったが、こんな風に何時間にも渡って旧知の友のように話し込んでしまうことはなかった。なにしろ、
さっき会ったばかりなのだ。それが、こんなに長い間、少しも嫌な思いをしないでいられるなんて、古い友人でもありえなかった。もうすぐ列車が到着して、
それで別れてしまうのが残念だなんて。ずっと列車が着かなければいいと思ってしまうなんて。
「着いたら……ちょっと、時間ある?すぐに行かなきゃならない?」
アブナーがそう考えていると、見透かしたようにブラッドそう言った。列車が減速しだして、いよいよ到着間近になった頃だった。
「いや、別に。今日中に着ければ」
「じゃあスタンドでコーヒーでもどう?」
いいとこ知ってるんだ、ペーパーバックが読めなかったお詫びに、ご馳走するからとブラッドが、屈託なく笑うものだから。
「そろそろ酒の時間だけどな」
アブナーは笑ってそう答えてしまったのだった。
夕方の混みあう時間の駅のコーヒースタンドという、とてもあわただしい場所でコーヒーを飲んだ。
どんなにちびちび飲もうと、店の中では長居が出来ないからといって駅のベンチに座ろうと、紙コップの中がカラカラになってしまうのには、
さほど時間はかからなかった。
「……それじゃ」
「ああ……」
何時間もあった列車の中とは違って、秒読みできるほどの時間しかないスタンドでは、あまり話は弾まなかった。
ぽつりぽつりと当り障りのない話しをするのが精一杯で本当に話したいことは、ほとんど口に出来なかった。
引き止めても悪いだろうしなという思いと、このまま一緒にいたい離れたくないという思いがせめぎあっていた。
どうしてそんな風に思ってしまうかは分からなかった。ただこのままにしたくないという悪あがきで胸がいっぱいだった。
「じゃ……」
どんなにのろのろ立ち上がろうと、いつかはその時が来てしまう。せいぜいがとこ握手をして、サヨナラをしなくてはいけないときが。
なんだか自分が哀愁ただよう映画なの中の、登場人物にでもなったような気分だった。別れがたくて離れがたくて、でもこの列車に乗らなくてはならない……
そうやって旅立ったあれはなんという映画だっただろう?そんなことよりも、自分とブラッドは恋人同士でも親友でもなんでもないのに、
これはどうしたことだろうかと考えた。もちろん答えが、そう簡単に出るはずもなかった。
「ありがとう、ブラッド。おかげで道中楽しかった」
「こちらこそ、楽しい時が過ごせたよ。ありがとう」
せめてこのぬくもりを覚えておこうと、名残りはつきないながらも手を離した。
「じゃ」
そう言ってアブナーは今度こそ出口に向かって歩き出した。
ブラッドのホテルはどこなんだろう?出口はこっちではないんだろうかという未練な考えが頭をもたげたが無理矢理ねじ伏せた。
視線がうまく定まらなかった。こんな人込みでぼーっとしていた日には、スリさん狙ってくださいと言っているようなものだから、しっかり歩かなくては思いつつ、
アブナーは自分が固いはずの地面を踏んでいるという感覚すらなかった。
「……エリック!」
声をかけられた。それから腕をかけられた。聞き覚えのあるような声に、おそるおそる振り返るとそこには、息せき切ったブラッドの姿があった。
捕まえられた腕の痛みが本当なら、どうやらこれは夢ではないようだった。
「ブラッド……?」
どうして?とアブナーが首を傾げていると、ブラッドはアブナーの手を取って、そこに紙片を握らせた。
「これ、このホテルにいるから」
「え?」
「今月一杯はいるから、よかったら……いや、よくなくても連絡してくれ、待ってるからっ」
「え……?」
言っていることの意味が分かるまでしばらくかかった。アブナーはなんだか泣きたくなった。
涙はこぼれおちることはなかったが。
もう公開も終わるってのにやっとです!
やっと『血襟@みゅんへん』スタートです!!
長かった……(涙)。
しかし話は始まったばかり、気を引きしめていかないと!
途中にも書きたいところはイロイロあれど
1番書きたいのはラストのあたりなので
そこまでがんばるぞー!おー!!
こういうのをやることで感想を書いているようなものだし(笑)。